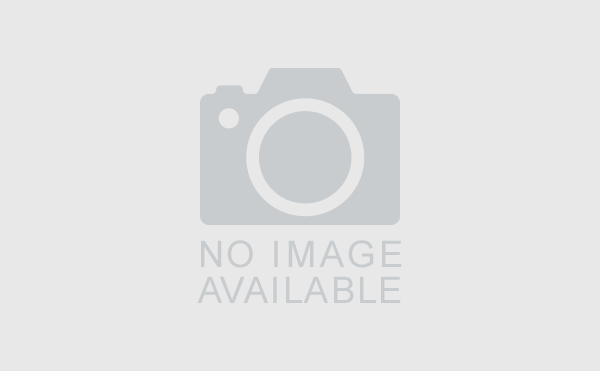映像コンテンツをどうやって活用するか?
動画を作っただけでは何も起こらない

映像コンテンツを作ること自体は、もう難しくない時代です。「スマホだけで作れます!」というように、「どうやって作るか」が話題になりますが、それよりも「どう活用するか」が問題です。
その前に、映像コンテンツというものの役割を考えてください。役割によって、映像の作り方も活用の仕方も全く違ってくるからです。
映像コンテンツの主な役割
ブランディング動画
会社・事業案内ビデオ .etc
その会社・事業のコンセプトやイメージを定着させるために、かなりの長期間にわたって継続して作り続ける必要がる動画。直接的に売上に貢献したりすることはないが、社会的意義を宣言するなど、その会社・事業をアピールするのが役割。
「ビジネス用の動画」と言うと、真っ先に思い浮かぶのがこのタイプだが、一説には、対費用効果を生むのは、年商100億円以上の企業だけとも言われている。
形だけ真似て、「バズ動画」として話題になっても、ほとんど効果がない動画が多く存在する。
販売用広告動画
- 商品・サービス案内ビデオ .etc
販促用として一般的な動画。
ホームセンターの売り場で流れる、商品の使い方・特徴などを解説した動画が良い例。
その商品の「バーチャル営業マン・セールスマン」として、顧客に商品やサービスの説明をして、「問い合わせ」「購入」を促すのが役割。
コスト削減用動画
研修・教育用ビデオ .etc
組織の内部資料としての動画。
例えば、アルバイトに対する、定型の教育や、従業員に対する研修のうち、定型的な部分を動画にして、当事者が自主的に閲覧できるようにすることで、組織全体の大幅なコスト削減が図れる。
実際は、教育・研修する担当者が「楽な仕事」を失うことになるので、反対されることもある。
商品としての動画
セミナービデオ .etc
受講生を前にしたセミナーを撮影して、セミナーの疑似体験動画として制作する場合もあるが、講師が自宅でカメラを前に講義を行う形の動画も多い。
頭の中に「商品になり得る情報」がある場合は、最もシンプルに商品になるのがセミナービデオ。
それ自体が販売商品。
公共情報動画
施設利用手順/啓発用映画 .etc
地域の自治体などが施設の利用案内をわかりやすく解説するための動画。
また、チラシなどで行う「振り込め詐欺への注意喚起」などをより効果的に周知させるために、ドラマ形式にした動画。
対象者に必要な情報を理解させるのが役割。
最も活用しやすい動画から作る
ビジネスで最も重要なのは、マーケティングです。そして、マーケティングは、必ずしも発信側の思い通りにはならない、難しい分野でもあります。
上記の様々な動画も、マーケティングツールとして活用することになるので、活用法を踏まえた上で設計して、実際に活用する必要があります。つまり、作ったからと言って、すぐに成果が出る使い方ができるとは限らない難しさがあります。
しかし、上記の中で一つだけ例外があります。それが、「コスト削減用動画」です。
具体的には、「ビデオマニュアル」や「教則ビデオ」のようなものだと思ってください。
「伝えるべきこと」のうち、4割くらいは定型の内容という場合がよくあります。
この「定型の部分」をビデオにして、各自、都合に合わせて事前に見ておくことにするだけでも、説明する人の時間を使わずに済みます。
また、
- 一度聞いただけでは理解しにくい説明
- 後から改めて確認したくなるはずの説明
をビデオにしておくことで、問い合わせに答えるコストが激減することがイメージできると思います。
コストは、単純に、「答える人の時間給」で計算できる筈です。
- 労働時間の短縮
- 生産性の向上
に興味がない人には響かない話でしょう。
ともかくも、「動画を制作して活用したい」ということであれば、難しいマーケティングに関係のない、「コスト削減用動画」を作ることをオススメします。自分たちで活用さえすれば、元が取れるものだからです。
実例・トレーニングビデオ
ある企業で採用された例をご紹介します。
一つの工業製品が発売になった際、その製品を扱うことになる販売者・修理担当者を一同に集めて、製品の仕様説明・修理のための分解実演などを行います。
これを、「トレーニング研修」と読んでいましたが、大人数を各地から招集する費用は膨大でした。
この内容を「トレーニングビデオ」という形にまとめて、各地の担当者に配布する形にすることで、大幅なコスト削減になるだけでなく、資料としても見直せるものになりました。
このような「内部資料としての映像」は、対象が顧客ではないので、「見栄え」よりも「簡潔なわかりやすさ」を優先できるのが特徴です。
素材の撮影も、必ずしも専門業者に依頼せずとも、内部のスタッフで充分対応可能です。
まとめ
今回は、
- 動画コンテンツの種類と役割
- 「コスト削減用動画」がオススメ
という話をしました。
順次、「コスト削減用動画」以外の動画についても、活用法を解説していきます。